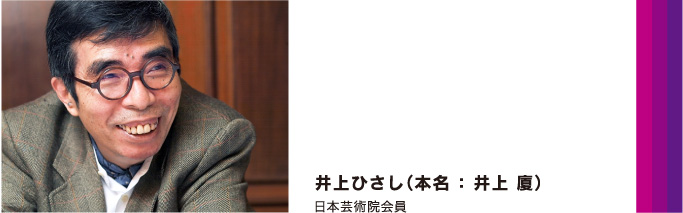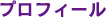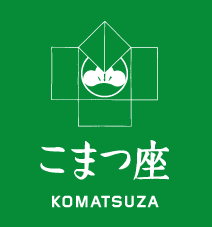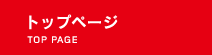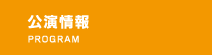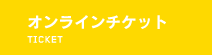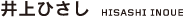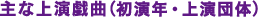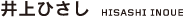

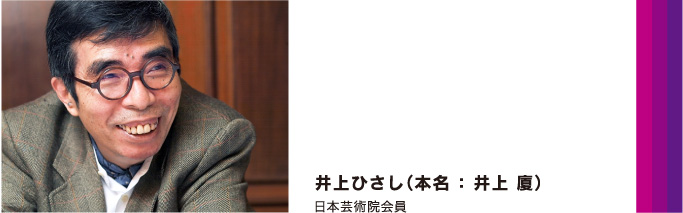
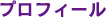
1934年(昭和9年)11月16日。山形県東置賜郡小松町(現・川西町)に生まれる。
中学三年になった49年、岩手県一関市へ家族が移り住み、同年秋には母や兄と離れて宮城県仙台市にある児童養護施設「光が丘天使園」に弟と入所。この頃、友人に宛てた手紙で、将来作家になる固い決意を述べている。
50年、宮城県立仙台第一高等学校入学。在学中の三年間で千本の映画を鑑賞。映画評を「キネマ旬報」「映画と友」へ投稿し、しばしば掲載された。
53年、上智大学外文学部ドイツ文学科入学。一学期を終えたところで岩手県釜石市に帰省。母の営む屋台の手伝いをしながら図書館でアルバイトを始め、そこで文学全集や黄表紙集などを読み漁る。同年11月、国立釜石療養所の職員となる。
56年、上智大学外国語学部フランス語科に復学。寮費を含めた生活費のため様々なアルバイトに精を出し、11月には浅草フランス座の文芸部員兼進行係に採用される。ストリップショーの幕間に演じられる笑劇(コント)の台本を書くと同時に、たくさんのラジオドラマを書いては懸賞に応募し、賞金を稼いだ。この投稿を通じてNHKの学校放送部から声がかかり、放送作家として教育関連の番組を担当。60年に上智大学を卒業後は、さらに数多くのラジオ・テレビ番組を手掛ける。
64年、児童文学者の山元護久氏と共同執筆したNHKの連続人形劇『ひょっこりひょうたん島』が五年間にわたって放映され、国民的人気番組となる。
69年、劇団テアトル・エコーに書き下ろした戯曲『日本人のへそ』で演劇界にデビュー。小説、エッセイの分野にも活動の場を広げ、 72年には、戯曲『道元の冒険』で岸田戯曲賞と芸術選奨新人賞を、江戸戯作者群像を軽妙なタッチで描いた小説『手鎖心中』で直木賞を受賞。
76年の3月から7月、オーストラリア国立大学アジア学部日本語科客員教授としてキャンベラに滞在。
その後も精力的に執筆活動を続け、ベストセラーとなった『吉里吉里人』を始め、発表された小説・戯曲で文学・演劇の各賞を受賞。後には多くの文学賞等の選考委員も務める。
84年に自作の戯曲のみを上演する劇団こまつ座を旗揚げ。『頭痛肩こり樋口一葉』を皮切りに座付作者として次々に新作を書き下ろす。
87年、生まれ故郷へ寄贈した7万冊の蔵書をもとにした図書館が川西町に開館。原稿の遅さから「遅筆堂」と名乗っていたことにちなんで「遅筆堂文庫」と命名。これを機に「生活者の視点で自らの暮らしを見つめなおそう」と、遅筆堂文庫・生活者大学校の開校を提唱し、校長として全国から参加する受講者とともに、農業問題を中心とするさまざまなテーマに取り組んだ。(生活者大学校は現在も川西町にて毎年11月に開校)
日本文藝家協会理事、劇団協議会理事、劇作家協会会長、日本ペンクラブ会長、仙台文学館館長、吉野作造記念館名誉館長、千葉県立市川市文化振興財団理事長などを歴任。
また、九条の会呼びかけ人、世界平和アピール七人委員会に名を連ね、社会問題にも積極的に発言した。 01年には「知的かつ民衆的な現代史を総合する創作活動」で朝日賞を受賞。04年、文化功労者に選ばれる。09年日本放送協会放送文化賞。恩賜賞日本芸術院賞を受賞。10年「長年にわたり演劇界に多大な貢献をしてきた」ことにより読売演劇大賞 芸術栄誉賞を受賞。同年故郷山形県より山形県県民栄誉賞受賞。
2010年4月9日永眠(75歳)。
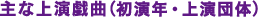
『日本人のへそ』 (1969 テアトル・エコー)
『表裏源内蛙合戦』( 1970 テアトル・エコー)
『十一ぴきのネコ』(1971 テアトル・エコー)
『道元の冒険』(1971 テアトル・エコー)
『珍訳聖書』(1973 テアトル・エコー)
『藪原検校』( 1973 五月舎)
『天保十二年のシェイクスピア』(1974 西武劇場)
『それからのブンとフン』(1975 テアトル・エコー)
『たいこどんどん』(1975 五月舎)
『四谷怪談』(1975 芸能座)
『雨』(1976 五月舎)
『浅草キヨシ伝』(1977 芸能座)
『花子さん』(1978 五月舎)
『日の浦姫物語』(1978 文学座)
『しみじみ日本・乃木大将』(1979 芸能座)
『小林一茶』( 1979 五月舎)
『イーハトーボの劇列車』( 1980 五月舎)
『国語事件殺人辞典』(1982 しゃぼん玉座旗揚げ公演)
『吾輩は漱石である』(1982 しゃぼん玉座)
『化粧』(1982 地人会)
『もとの黙阿弥』(1983 新橋演舞場)
『芭蕉通夜舟』(1983 しゃぼん玉座)
『頭痛肩こり樋口一葉』(1984 こまつ座旗揚げ公演 )
<昭和庶民伝三部作>(こまつ座)
『きらめく星座』( 1985) 、『闇に咲く花』( 1987)、『雪やこんこん』( 1987)
『國語元年』( 1986 こまつ座)
『泣き虫なまいき石川啄木』(1986 こまつ座)
『花よりタンゴ』(1986 こまつ座)
『キネマの天地』(1986 松竹)
『イヌの仇討』(1988 こまつ座)
『人間合格』( 1989 こまつ座)
『シャンハイムーン』( 1991 こまつ座)
『ある八重子物語』(1991 水谷八重子十三回忌追善・新派特別公演)
『中村岩五郎』(1992 地人会)
『マンザナ、わが町』( 1993 こまつ座)
『父と暮せば』( 1994 こまつ座)
『黙阿彌オペラ』( 1995 こまつ座)
『紙屋町さくらホテル』( 1997 新国立劇場こけら落とし公演)
『貧乏物語』(1998 こまつ座)
『連鎖街のひとびと』(2000 こまつ座)
『化粧二題』 (2000 こまつ座)
<東京裁判三部作>(新国立劇場)
『夢の裂け目』(2001)、『夢の泪』(2003)、『夢の痂』(2006)
『太鼓たたいて笛ふいて』(2002 こまつ座)
『兄おとうと』(2003 こまつ座)
『水の手紙 � 群読のために-』(2003 国民文化祭やまがた)
『円生と志ん生』(2005 こまつ座)
『箱根強羅ホテル』(2005 新国立劇場)
『私はだれでしょう』(2007 こまつ座)
『ロマンス』(2007 こまつ座・シス・カンパニー)
『少年口伝隊一九四五』(2008 世界P.E.Nフォーラム『災害と文化』に書き下ろし)
『ムサシ』(2009 こまつ座・ホリプロ・朝日新聞社・テレビ朝日・(財)埼玉県芸術文化振興財団)
『組曲虐殺』(2009 こまつ座&ホリプロ)
◆ 井上ひさし戯曲 主な海外公演
- ◎こまつ座 『父と暮せば』
- 2001年6月 ロシア・モスクワ(エトセトラ劇場)
2004年12月 中国・香港(香港芸術壽臣劇院)
『ムサシ』
2010年5月 ロンドン(バービカン・シアター)
- ◎地人会 『化粧』
- ●渡辺美佐子 主演
1986年 パり(10st)、1987年 アメリカ(24st)
1989年 カナダ、ブリュッセル(11st)
●ヌリア・エスペール 主演
1990年 スペイン(バレンシア、バルセロナ、マドリッド、メキシコ巡演)
●フランシス・ドゥ・ラ・トゥール 主演
1993年 イギリス
●アンジェリカ・アラゴン 主演
1997年 メキシコ(日本人メキシコ移住100周年記念行事)
『藪原検校』
1990年 イギリス・エジンバラ国際演劇祭
1993年 香港、アメリカ、イギリス
1995年 トロント、1997年 韓国、パリ
2000年 ニュージーランド
その他、内外の劇団による海外公演が各地で行われ、中でも六カ国語の対訳本を刊行中の『父と暮せば』は、これまで、フランス、ロシア、中国、イギリス、カナダ、アメリカ、ドイツなどで上演、リーディングされている。
『父と暮せば』対訳シリーズ
英文対訳 『THE FACE OF JIZO』 ロジャー・パルバース 訳
ドイツ語対訳 『DIE TAGE MIT VATER』 イゾルデ・浅井 訳
イタリア語対訳 『MIO PADRE』 フランコ・ジェルヴァジオ/青山愛 訳
中国語対訳 『和8r8r在一起』 李錦琦 訳
ロシア語対訳 『ЖИЗНЬ С ОТЦОМ』米原万里 訳
仏文対訳 『QUATRE JOURS AVEC MON PERE 』 カンタン・コリーヌ 訳
各1,000円(税込) こまつ座

(数字は年号・西暦)
「NHKひょっこりひょうたん島1~4」(山元護久/共著日本放送出版協会・64~65)、「ブンとフン」(朝日ソノラマ社・70)、「表裏源内蛙合戦」(新潮社・71)、「道元の冒険」(新潮社・71)、「手鎖心中」(文藝春秋・72)「モッキンポット師の後始末」(講談社・72)、「珍訳聖書」(新潮社・73)、「青葉繁れる」(文藝春秋・73)、「四十一番の少年」(文藝春秋・73)、「天保十二年のシェイクスピア」(新潮社・73)、「家庭口論」(中央公論社・74)、「薮原検校」(新潮社・74)、「いとしのブリジット・ボルドー」(講談社・74)「イサムよりよろしく」(文藝春秋・74)「ドン松五郎の生活(上・下)」(新潮社・75)、「合牢者」(文藝春秋・75)、「井上ひさしコント集」(講談社・75)、てんぷくトリオのコント(1~3)」(サンワイズ・エンタープライズ・75)、「浅草鳥越あずま床」(新潮社・75)、「続・家庭口論」(中央公論社・75)、「おれたちと大砲」(文藝春秋・75)、「日本亭主図鑑」(新潮社・75)、「たいこどんどん」(新潮社・75)、「新東海道五十三次山藤章二・絵」(文藝春秋・76)、「偽原始人」(朝日新聞社・76)、「新釈遠野物語」(筑摩書房・76)、「雨」(新潮社・76)「井上ひさし笑劇全集」(講談社・76)、「ブラウン監獄の四季」(講談社・77)、「黄色い鼠」(文藝春秋・77)、「十二人の手紙」(中央公論社・78)、「ファザー・グース第1集」(青銅社・78)、「さそりたち」(文藝春秋・79)、<井上ひさしエッセイ集①~⑩>①「パロディ志願」②「風景は涙にゆすれ」③「ジャックの招待」④「さまざまな自画像」⑤「聖母の道化師」⑥「遅れたものが勝ちになる」⑦「悪党と幽霊」⑧「死ぬのがこわくなくなる薬」⑨「文学強盗の最後の仕事」⑩「餓鬼大将の論理」(中央公論社・79~94)、「戯作者銘々伝」(中央公論社、79)、「しみじみ日本・乃木大将」(新潮社・79)、「他人の血」(講談社・80)、「小林一茶」(中央公論社・80)、「花石物語」(文藝春秋・80)、「喜劇役者たち」(講談社・80)、「下駄の上の卵」(岩波書店、80)、「イーハトーボの劇列車」(新潮社・80)、「私家版日本語文法」(新潮社・81)、「ひさし・章二巷談辞典」(文藝春秋・81)、「吉里吉里人」(新潮社・81)、「ことばを読む」(中央公論社・82)、「井上ひさしの世界」(白水社・82)、「本の枕草子」(文藝春秋・82)、「国語事件殺人辞典」(新潮社・82)、「吾輩は漱石である」(集英社・82)、「にっぽん博物誌」(朝日新聞社・83)、「ライオンとソフトクリーム高橋透・絵」(ひさかたチャイルド・83)、「もとの黙阿弥」(文藝春秋・83)、「化粧」(集英社・83)、「仇討」(中央公論社・83)、「井上ひさし全芝居全七巻」(新潮社・84~10)、「月なきみそらの天坊一座」(新潮社・84)、「空き缶ユートピア」(集英社・84)、「自家製文章読本」(新潮社・84)、「頭痛肩こり樋口一葉」(集英社・84)、「四捨五入殺人事件」(新潮社・84)、「江戸紫絵巻源氏」(話の特集・85)、「腹鼓記」(新潮社・85)、「きらめく星座」(集英社・85)、「不忠臣蔵」(集英社・85)、「馬喰八十八伝」(朝日新聞社・86)、「國語元年」(新聞社・86)、「泣き虫なまいき石川啄木」(新聞社・86)、「花よりタンゴ」(集英社・86)、「野球盲導犬チビの告白」(実業之日本社・86)、「キネマの天地」(文藝春秋・86)、「ああ幕があがる井上芝居ができるまで」(こまつ座/共著朝日新聞社・86)、「ナイン」(講談社・87)、「雪やこんこん」(朝日新聞社・87)、「闇に咲く花」(講談社・87)、「イヌの仇討」(文藝春秋・87)、「井上ひさしのコメ講座」(岩波ブックレット・89)、「日本語相談一~五」(朝日新聞社・89~92)、「四千万歩の男一~五」(講談社・90)、「人間合格」(集英社・90)、「決定版十一ぴきのネコ」(新潮社・90)、「江戸紫繪巻源氏」(話の特集・90)、「ひょっこりひょうたん島1~13」(筑摩書房・90~92)、「シャンハイムーン」(集英社90)、「とくとく歌仙」(丸谷才一・大岡信・橋本治/共著文藝春秋・91)、「続・井上ひさしのコメ講座」(岩波ブックレット・91)、「たそがれやくざブルース」(講談社・91)、「コメの話」(新潮社・92)、「ある八重子物語」(集英社・92)、「ニホン語日記」(文藝春秋・93)、「マンザナ、わが町」(集英社・93)、「どうしてもコメの話」(新潮社・93)、「『日本国憲法』を読み直す」(樋口陽一/共著講談社・94)、「百年戦争(上下)」(講談社・94)、「黙阿彌オペラ」(新潮社・95)、「ベストセラーの戦後史1・2」(文藝春秋・95)、「往復書簡拝啓水谷八重子様」(水谷良重/共著集英社)、「宮澤賢治に聞く」「樋口一葉に聞く」(こまつ座/共編著ネスコ・95)、「ニホン語日記2」(文藝春秋・96)、「本の運命」(文藝春秋・97)、「演劇ノート」(白水社・97)、「井上ひさしの農業講座」(こまつ座/共編著家の光協会・97)、「父と暮せば」(新潮社・98)、「井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室」(文学の蔵/編本の森・98)、「太宰治に聞く」(こまつ座/共編著ネスコ・98)、「菊池寛の仕事」(こまつ座/共編著ネスコ・99)、「対談集物語と夢」(岩波書店・99)、「東京セブンローズ」(文藝春秋・99)、「新日本共産党宣言」(不破哲三/共著光文社・99)、「わが友フロイス」(ネスコ・99)、「四千万歩の男忠敬の生き方」(講談社・2000)、「浅草フランス座の時間」(こまつ座/共著文春ネスコ・01)、「紙屋町さくらホテル」(小学館・01)、「夢の裂け目」(小学館・01)、「井上ひさしの大連写真と地図で見る満州」(こまつ座/共著小学館・02)、「にほん語観察ノート」(中央公論新社・02)、「井上ひさしの日本語相談」(朝日新聞社・02)、「あてになる国のつくり方フツー人の誇りと責任」(生活者大学校講師陣/共著光文社・02)、「太鼓たたいて笛ふいて」(新潮社・02)、「話し言葉の日本語」(平田オりザ/共著小学館・03)、「兄おとうと」(新潮社・03)、「座談会昭和文学史一~六」(小森陽一/共編著集英社・03)、「夢の泪」(小学館・03)、「憲法九条、今こそ旬」(九条の会/共著岩波ブックレット・04)、「イソップ株式会社和田誠・絵」(中央公論社・05)、<井上ひさしコレクション>「ことばの巻」「人間の巻」「日本の巻」(岩波書店・05)、「円生と志ん生」(集英社・05)、「ふふふ」(講談社・05)、「箱根強羅ホテル」(集英社・06)、「井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法いわさきちひろ・絵」(講談社・06)、「映画をたずねて井上ひさし対談集」(筑摩書房・06)、「夢の痂」(集英社・07)、「ボローニャ紀行」(文藝春秋・08)、「ロマンス」(集英社・08)、「ムサシ」(集英社・09)、「ふふふふ」(講談社・09)、「組曲虐殺」(集英社・10)、「井上ひさし全選評」(白水社・10)、「一週間」(文藝春秋・10)、「東慶寺花だより」(文藝春秋・10)、「井上ひさしの言葉を継ぐために」(岩波ブックレット・10)、「この人から受け継ぐもの」(岩波書店・10)、「日本語教室」(新潮社・11)、「グロウブ号の冒険」(岩波書店・11)、「創作の原点ふかいことをおもしろく」(PHP研究所・11)、「黄金の騎士団」(講談社・11)、「演劇人井上ひさし」(白水社・11)、「井上ひさしの読書眼鏡」(中央公論新社・11)、「一分ノ一(上下)」(講談社・11)、「言語小説集」(新潮社・12)、「ガリバーの冒険 安野光雅・絵」(文藝春秋・12)、「水の手紙 萩尾望都・絵」(平凡社・13)、「少年口伝隊一九四五」(講談社・13)、「井上ひさしと考える 日本の農業」(家の光協会・13)


| 1958年 |
第13回芸術祭賞脚本奨励賞(『うかうか三十、ちょろちょろ四十』) |
| 1969年 |
第9回日本放送作家協会賞最優秀番組賞(「ひょっこりひょうたん島」) |
| 1970年 |
第12回日本レコード大賞童謡賞(「ムーミンのテーマ」) |
| 1971年 |
第6回斎田喬戯曲賞(『十一ぴきのネコ』) |
| 1972年 |
第17回岸田戯曲賞・芸術選奨新人賞(『道元の冒険』) |
| 〃 |
第67回直木賞(「手鎖心中」) |
| 1979年 |
第14回紀伊國屋演劇賞個人賞(「しみじみ日本・乃木大将」「小林一茶」) |
| 1980年 |
第31回讀賣文学賞・戯曲部門(『しみじみ日本・乃木大将』『小林一茶』) |
| 1981年 |
第2回日本SF大賞(「吉里吉里人」) |
| 〃 |
第33回讀賣文学賞・小説部門(「吉里吉里人」) |
| 1982年 |
第13回星雲賞・日本長編部門 (「吉里吉里人」) |
| 1986年 |
第20回吉川英治文学賞(「腹鼓記」「不忠臣蔵」) |
| 1988年 |
第15回テアトロ演劇賞(昭和庶民伝三部作の完結) |
| 1991年 |
第27回谷崎潤一郎賞(『シャンハイムーン』) |
| 1998年 |
第9回農民文化賞 |
| 1999年 |
第9回イーハトーブ賞 |
| 〃 |
第47回菊池寛賞(「東京セブンローズ」の完成など) |
| 2001年 |
第71回朝日賞(知的かつ民衆的な現代史を総合する創作活動) |
| 〃 |
第3回織部賞 |
| 2003年 |
第44回毎日芸術賞(『太鼓たたいて笛ふいて』をはじめとする劇作活動) |
| 〃 |
第6回鶴屋南北戯曲賞(戯曲『太鼓たたいて笛ふいて』) |
| 2004年 |
文化功労者顕彰 |
| 2009年 |
第60回日本放送協会放送文化賞(放送文化の向上に功績) |
| 〃 |
第65回恩賜賞日本芸術院賞(戯曲を中心とする広い領域における長年の業績) |
| 2010年 |
第17回読売演劇大賞芸術栄誉賞 |
| 〃 |
山形県県民栄誉賞 |